ざっくりわかる「RS-232C」
「RS-232C」って聞いたことある?
実はこれ、ずーっと昔からある通信規格なんだけど、今でも機械の設定やセンサー、測定器など身近なところで大活躍しているんだ。
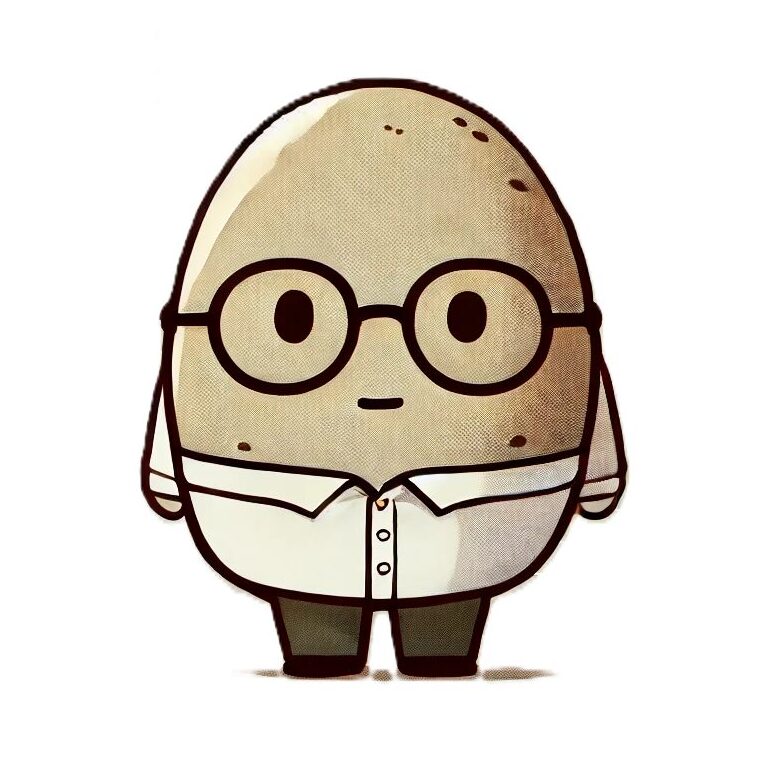
USBが主流なのに、なんで今も使われるの?
実はそこには、シンプルだけど超頼れる秘密があるんだよ。
今日は、そんな意外と知られていない「RS-232C」の世界をわかりやすく紹介していくよ!
RS-232Cってそもそも何?
RS-232Cとは、パソコンや機械同士がケーブルを使って会話するための「通信ルール」のことだよ。
このルールに沿って、コネクタ(接続端子)の形やケーブルの配線方法が決められているから、機械が違ってもお互いスムーズにデータを送り合うことができるんだ。
USBにも「決まった形のコネクタ」があるよね。RS-232Cも同じように、「決まったルールで作られた専用のコネクタ」を使って通信しているんだ。
ちなみに「RS」は「Recommended Standard(推奨規格)」の略で、「232」はその規格番号のこと。
つまり、「232番目に決められた通信の決まり」っていう意味なんだよ。

シリアル通信ってどんなイメージ?
RS-232Cは「シリアル通信」という方法でデータを送っているんだ。
シリアル通信って何?と思った人は、「1車線しかない道路」を想像してみて。
データを車だとすると、この道路では車が1台ずつ順番に通るしかないよね。
これが「シリアル通信」。つまり、1つずつ順番にデータを送る通信のやり方だよ。
一方で「並列通信」は、複数の車線がある道路で、同時に複数の車(データ)を送れるイメージ。
シリアル通信は、一度に大量のデータは送れないけど、配線がシンプルで安定しているから、長い距離でも問題なくデータを送りやすいんだ。
RS-232Cは、そんなシンプルで確実な通信を使っているというわけだね。
並列通信との違い
さっき、シリアル通信を「1車線道路」に例えたよね。
これに対して、並列通信は「複数車線の道路」をイメージするとわかりやすいよ。
並列通信では、同時に複数の車(データ)を一気に送るから、短い距離なら高速でたくさんのデータを送れるというメリットがあるんだ。
でも、いいことばかりじゃない。
道路の車線(配線)が増えると、車同士(データ同士)のタイミングがズレたり、ノイズ(電気的な雑音)で信号が乱れやすくなるんだ。そのため、距離が長くなるほど信号が乱れて通信が不安定になるリスクが高くなっちゃう。
一方、シリアル通信はデータを順番に送るので、配線がシンプルでノイズの影響を受けにくい。その結果、並列通信ほど高速じゃないけど、長距離でも安定した通信ができるんだ。
- シリアル通信:スピードは普通だけど長距離でも安定。
- 並列通信:短距離なら高速だけど、距離が長くなると不安定になりやすい。
RS-232Cが今も使われ続けているのは、まさにこの「安定性」を重視する場面がたくさんあるからなんだよ。
