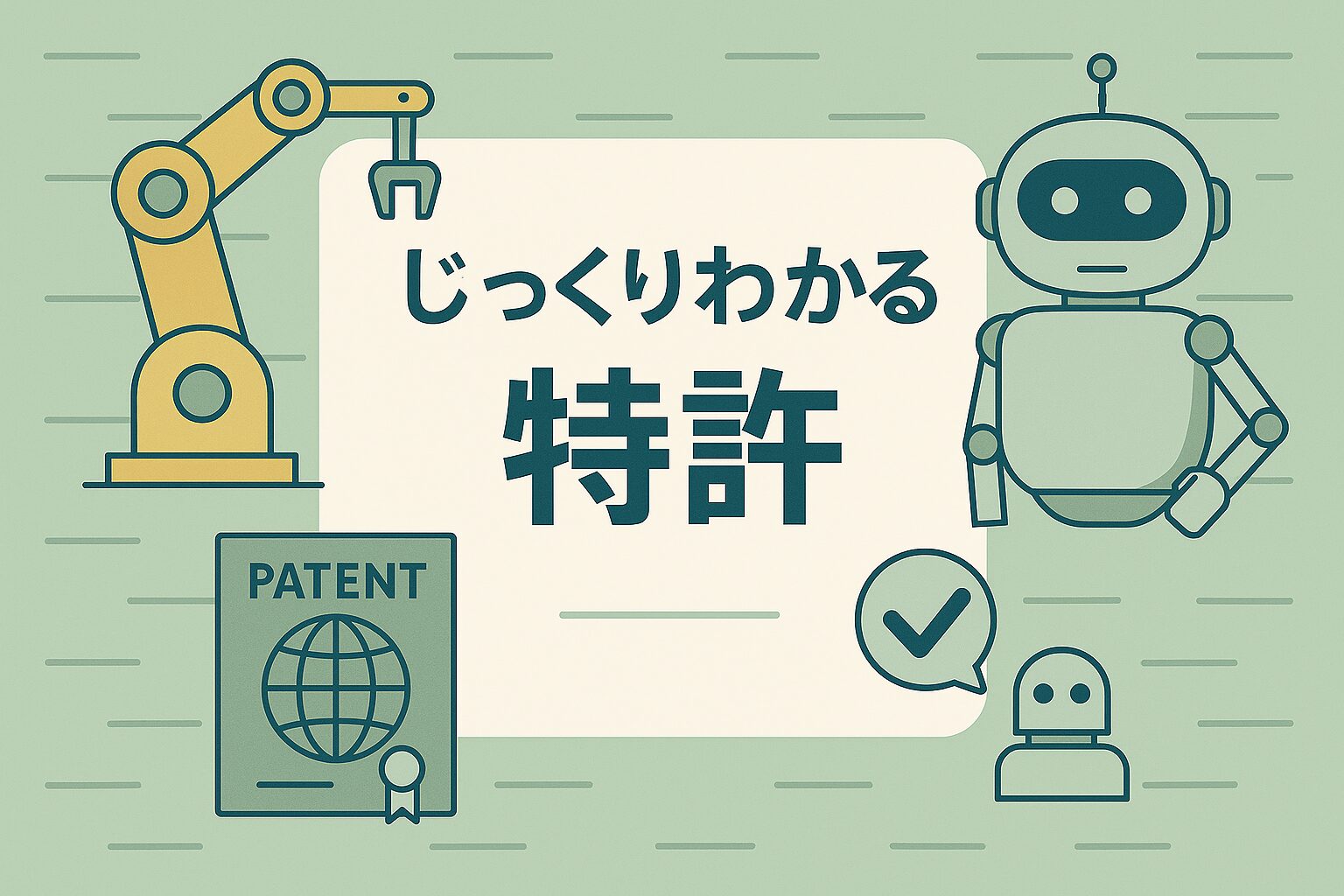じっくりわかる「棚卸し」
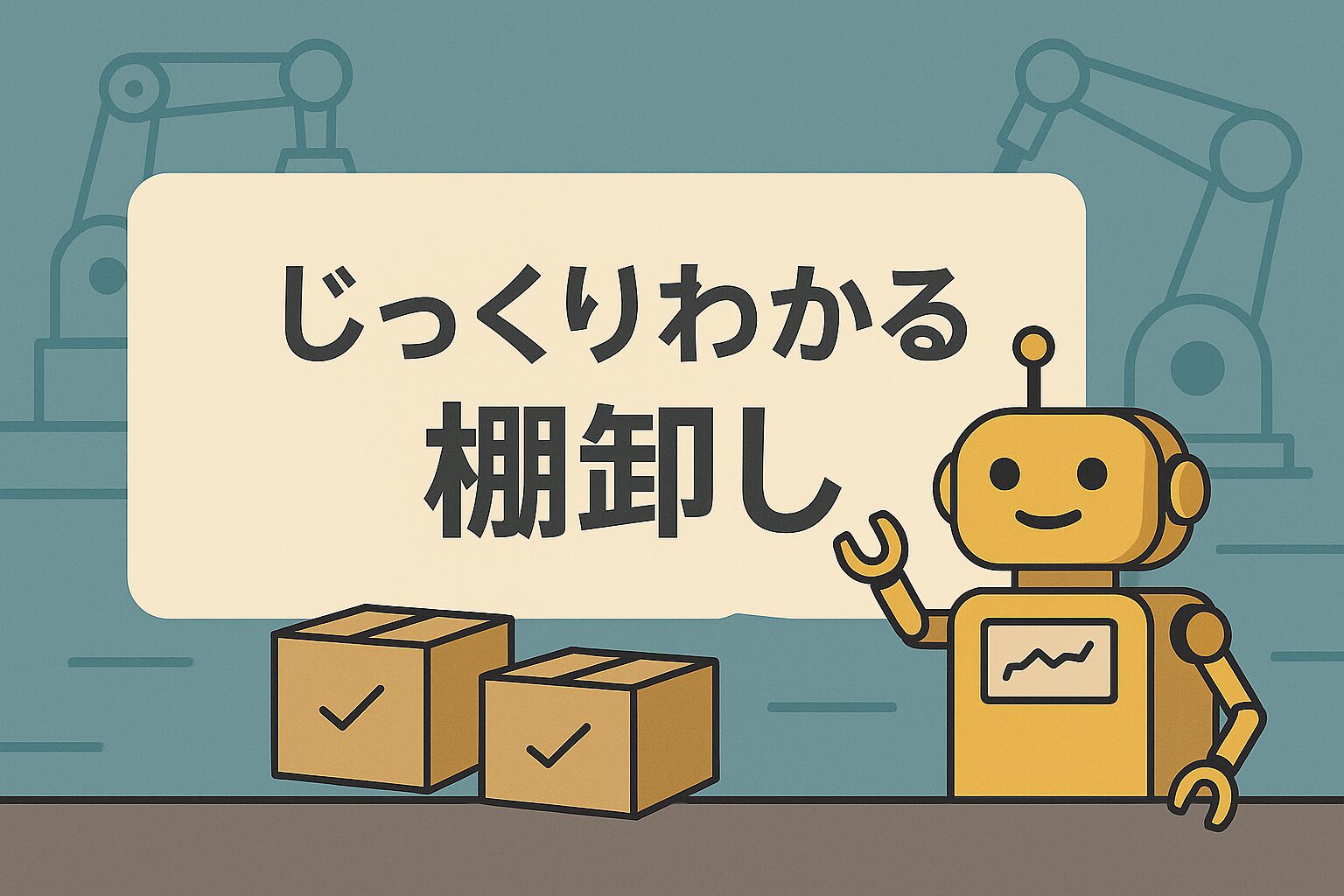
棚卸しって聞いたことあるけど、何してるの?
「棚卸し」って言葉、製造業で働いているとよく聞きますよね。
「期末にやるやつ」「在庫を数えるやつ」――そんなイメージを持っている人も多いと思います。
でも実際に棚卸しがどんなことをしていて、なぜそれが重要なのか、説明できる人は意外と少ないかもしれません。
筆者自身も最初は「なんでわざわざ全部数え直すんだろう?」と思っていました。
結論から言うと、棚卸しは単なる在庫チェックではありません。
それは、「帳簿と現物が本当に合っているかを確かめる作業」であり、
言い換えれば、**会社の管理体制の信頼性を示す大事な“証明作業“なんです。
この記事では、製造業で行われる棚卸しについて、
- 誰がやるの?
- なんで必要なの?
- 何をチェックしてるの?
- 間違ってたらどうなるの?
といった素朴な疑問に答えながら、現場目線でわかりやすく棚卸しの全体像を解説していきます。
棚卸しは誰がやる?外部の人?それとも社内?
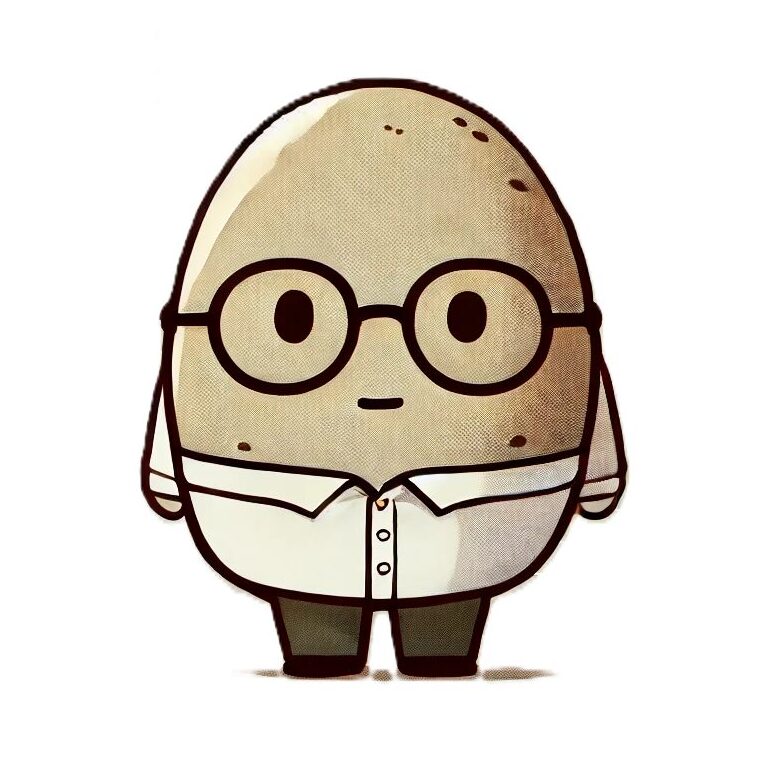
実はほとんど社内でやってます
「棚卸し」って聞くと、なんとなく“監査っぽい”イメージを持っていて、
外部の人が来てチェックしているものだと思っていませんか?
実は、棚卸しは基本的に社内で実施する作業です。
工場の担当者が在庫を一つひとつ確認したり、事務所側で帳簿と付き合わせたりと、
現場と管理部門が連携して行う、定期的な社内イベントなんです。
ただし、外部の監査人(会計監査)や税務署がその棚卸しの結果をチェックしに来ることはあります。
特に期末のタイミングでは、監査人が棚卸しの様子を「抜き打ち」で見に来ることも。
つまり棚卸しは、
- 実施:社内の手作業(現場+経理)
- 確認:外部の監査人や税務署があとでチェック
という役割分担になっているんです。
なんでやるの?合ってなかったらどうなるの?
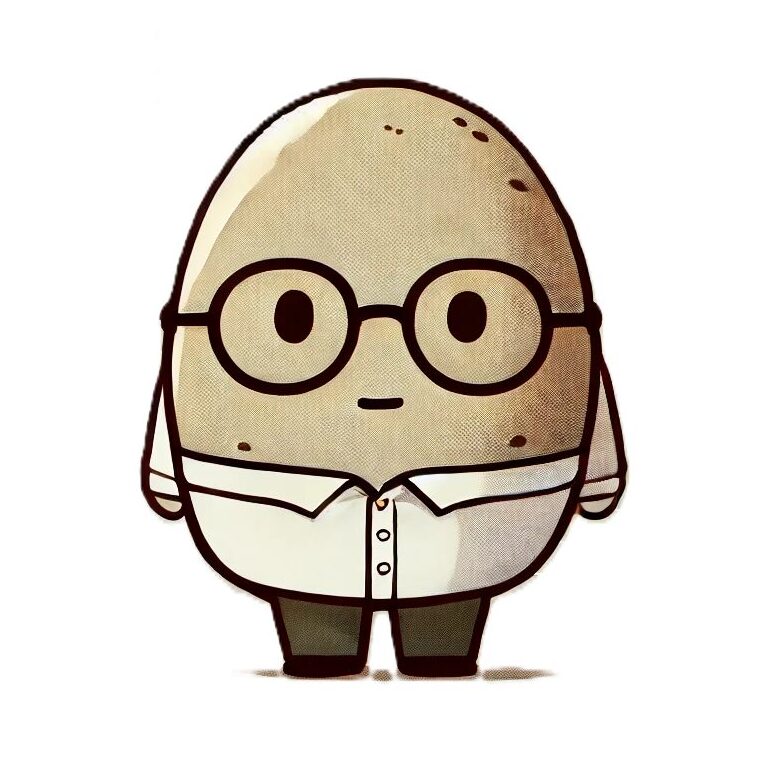
合ってなかったら「不正・管理不備」があると疑われます
棚卸しの目的は、帳簿と現物がちゃんと合っているか確認すること。
なぜそれが大事かというと――
ズレている=管理できていない証拠になり、信用を失うからです。
たとえば、帳簿では「あるはずの部品」が実際には現場にない。
でも誰も理由を説明できない。
この時点で、会社としての管理の甘さが露呈します。
- 会計監査で「内部統制に問題あり」と指摘される
- 財務諸表の信頼性が下がる(投資家や銀行からの評価に響く)
- 税務調査で追徴課税されるリスクが上がる
- 社内でも「どこかで不正があるのでは?」という不信が広がる
つまり、棚卸しはただの在庫確認じゃありません。
「ちゃんと管理されています」と社内外に証明する、会社の信用を守る作業なんです。
ズレがあること自体より、ズレを放置することの方が致命的。
だからこそ、定期的に棚卸しを行って、記録と実物をきちんと照合する必要があるんです。
製造業ならではの特徴
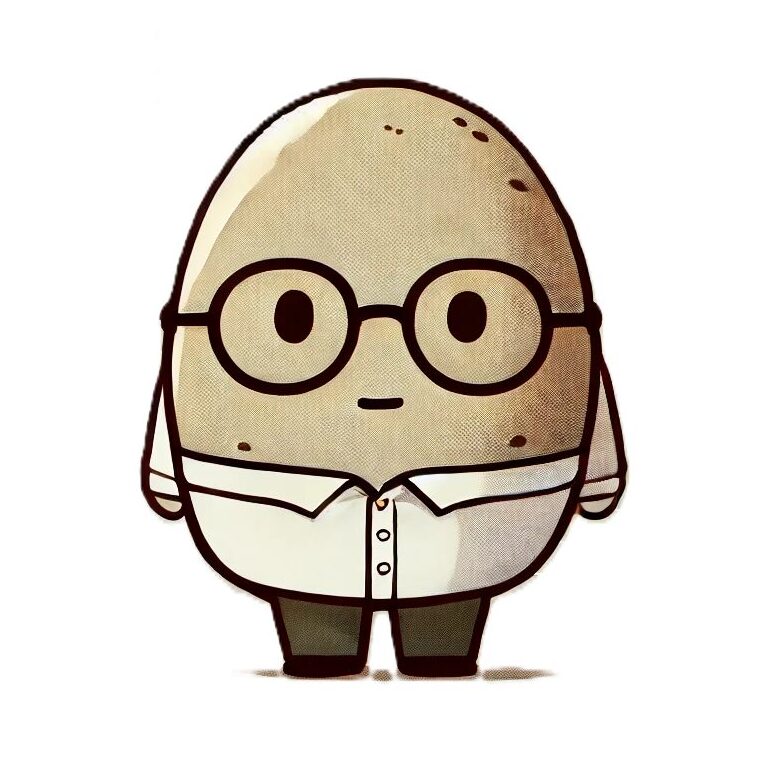
製造業の棚卸しは「数えるだけ」じゃ済まないんです!
棚卸しといえば「在庫を数える」というイメージですが、製造業ではそう簡単にはいきません。
なぜなら、ただ完成品が並んでるわけじゃないからです。
🔄 「仕掛品」があるからややこしい
製造業では、製品が完成するまでに複数の工程を経ます。
その途中にある部品や中間品――つまり仕掛品も、棚卸しの対象です。
でも、仕掛品ってこんな疑問が出てきます:
- どの工程まで終わってる?
- これは「製品の一部」なのか、「まだ材料」なのか?
- どうやって評価する?金額はどうつける?
こうした判断が必要なため、ただ数えるだけでは終わらないのが製造業の棚卸しなんです。
📦 対象の幅が広い
製造業では以下のようなものすべてが棚卸し対象になります:
- 原材料(購入したままの部品や材料)
- 仕掛品(加工途中のもの)
- 完成品(出荷待ちの製品)
- 保守用部品、試作品、研究中の試料 など…
つまり、製造現場・倉庫・試験室など、社内のあらゆる場所が関係してくるわけです。
🤝 現場と経理の連携が必須
製造業の棚卸しでは、経理担当だけでなく、現場の担当者がいないと棚卸しが成り立ちません。
- 現物をどこに置いてあるか
- これは完成品か、途中品か
- 特別対応中で使えないものかどうか
…といった情報は、現場の人が一番よく知っているからです。
つまり製造業の棚卸しは、
現場の感覚 × 会計のルール
この2つをすり合わせる、調整力のいる仕事なんです。
実際の棚卸しってなにをするの?
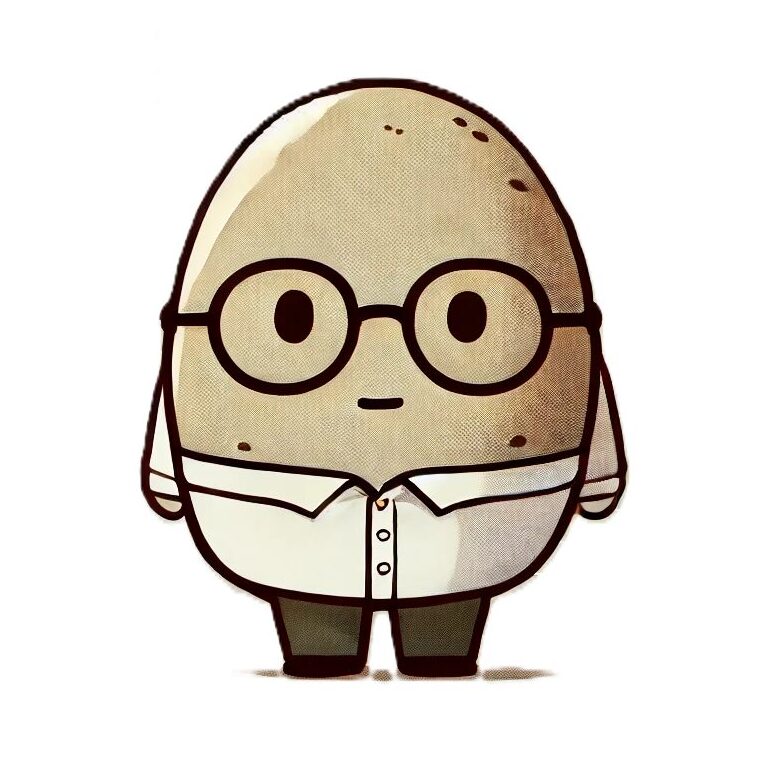
現場は意外とピリピリしてます
棚卸しというと「ただ在庫を数えるだけ」と思いがちですが、
実際にはかなり段取りが必要で、現場全体を巻き込む一大イベントになります。
📝 ① 棚卸しリストを作成
まずは、あらかじめ在庫一覧(帳簿上の数量)をもとにカウント用のリストが用意されます。
対象になるのは、原材料、仕掛品、完成品、工具や予備品など。
🧮 ② 現物を目で見て数える(実地棚卸し)
実際に現場へ行って、在庫品を一つひとつ数えていきます。
バーコードで読み取る場合もありますが、基本は人の手で確認する作業。
筆者の会社でも最近棚卸しがありましたが、
その日は「現場立ち入り禁止」の貼り紙があちこちに**。
理由は簡単で、
数えてる途中に誰かが物を動かしたら、数が合わなくなるから
です。
でも、事情を知らずに現場に入ってしまった人がいて、
「今、棚卸し中なんで!中に入らないで!」と注意される一幕も。
こういうの、本当に“棚卸しあるある”です。
🔍 ④ 数が合ってるかを帳簿と照合する
カウントが終わったら、記録された在庫数と帳簿上のデータを突き合わせます。
ズレがあれば、その原因を探って調整します(記録ミス?実物が紛失?工程飛ばし?)。
🧾 ⑤ 最後に調整・記録
最終的に「この時点ではこれだけ在庫があった」という記録を確定し、
会計や社内の在庫データに反映されて完了です。
棚卸しって、「ただ在庫を数える」だけじゃなくて、
数えるための段取りや環境づくりも含めて、現場が一丸になって取り組む作業なんだなと、筆者も実感しました。
棚卸しがうまくいかないとどうなる?
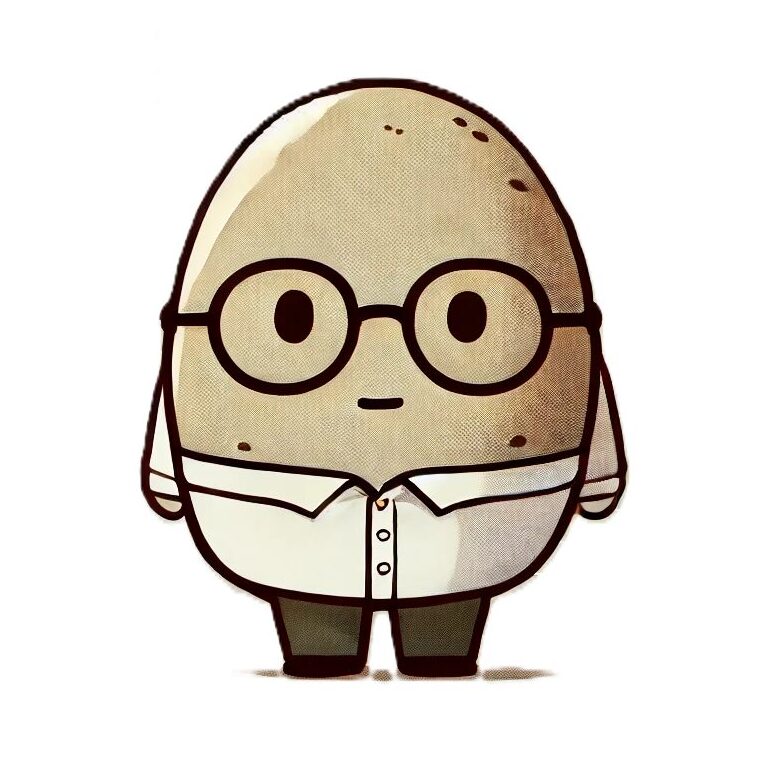
「信用」と「お金」に直接響きます
棚卸しのズレを放置したり、適当に済ませたりすると、
会社の信用や利益に直接ダメージが出る可能性があります。
❗ 信用を失うリスク
- 帳簿と現物が合っていない
- 差異の理由が説明できない
- 誰がどう管理していたかも曖昧
こうなると、社内的には「管理が甘い会社」、
社外からは「この会社、本当に大丈夫?」と見られてしまいます。
💸 財務や税務への影響
棚卸しは、決算時の在庫評価にも関わるため、
- 在庫を多く見積もれば → 利益が過大計上されて税金も増える
- 少なく見積もれば → 利益が少なくなって粉飾の疑いを持たれる
というリスクがあります。
- 不正や横領を疑われる
- 会計監査で「内部統制に不備あり」と指摘される
- 税務調査で追徴課税が入る可能性も
🧯「ズレがあること」より「説明できないこと」が問題
多少のズレは現場ではよくあることです。
でも問題なのは、それを放置して「なんとなく合ってる風」にしてしまうこと。
- なぜズレたのか?
- どの工程で?
- 管理方法に問題はなかったか?
こうした振り返りがあってこそ、棚卸しの意味があります。
「ただの数合わせ」と思っていた棚卸しが、
実は会社全体の信頼や安全性を支える、重要な基礎固めの作業だった――
というのが見えてきたんじゃないでしょうか。
まとめ:棚卸しは在庫管理の“定期健康診断”
ここまで見てきたように、棚卸しは単なる「在庫の数合わせ」ではありません。
- 帳簿と現物が合っているか?
- 管理はきちんとされているか?
- 不正や記録ミスの兆候はないか?
これらを目で見て確かめる、信頼の確認作業なんです。
とくに製造業では、仕掛品や部品などの扱いが複雑で、
現場の協力なしには正確な棚卸しはできません。
棚卸しは、会社が安全で健全に動いているかを確かめる“健康診断”のようなものなんです。